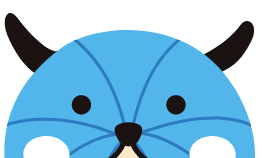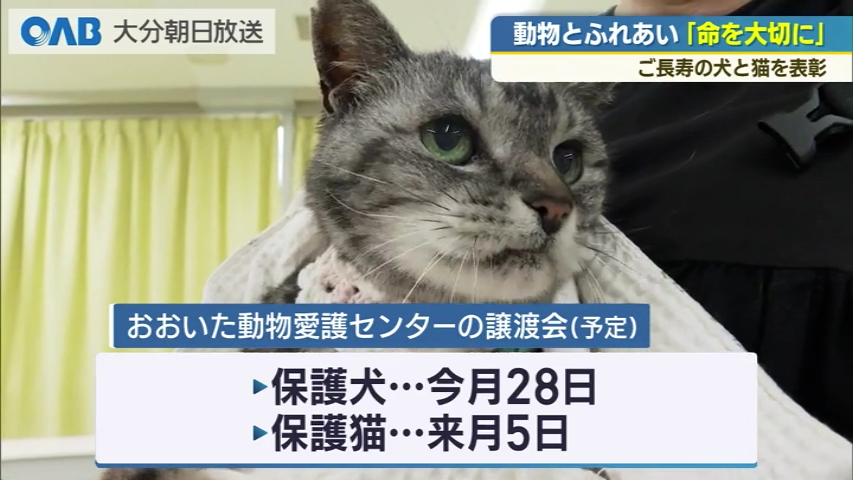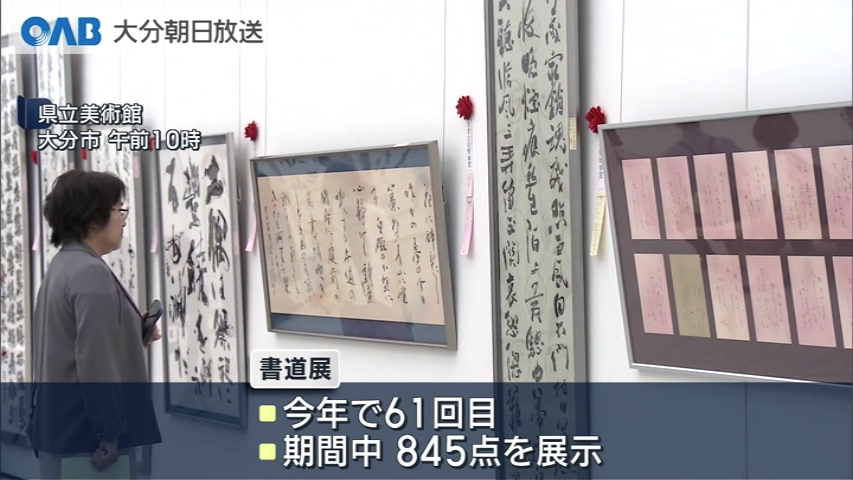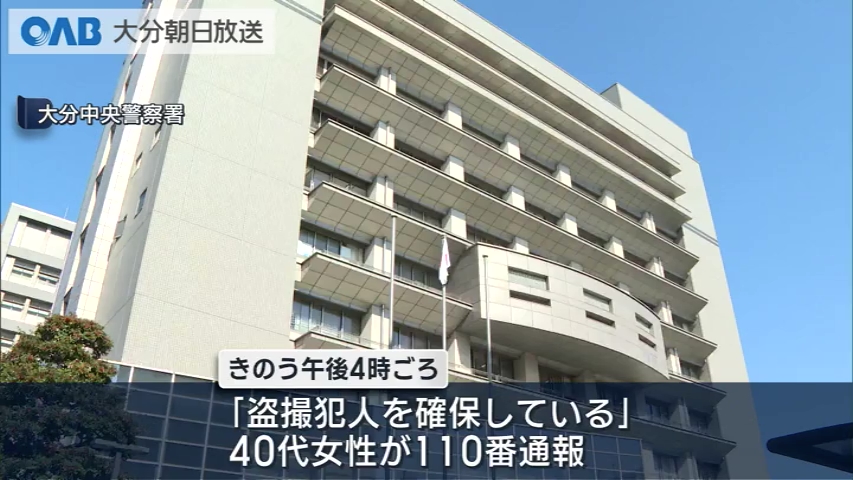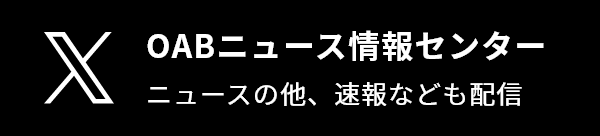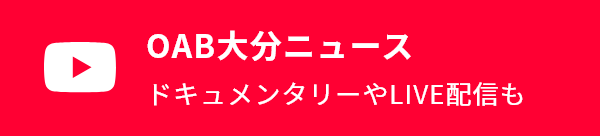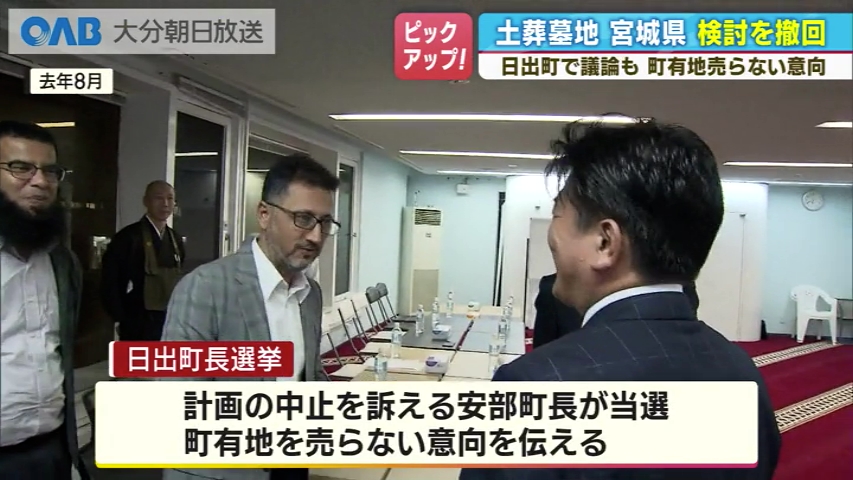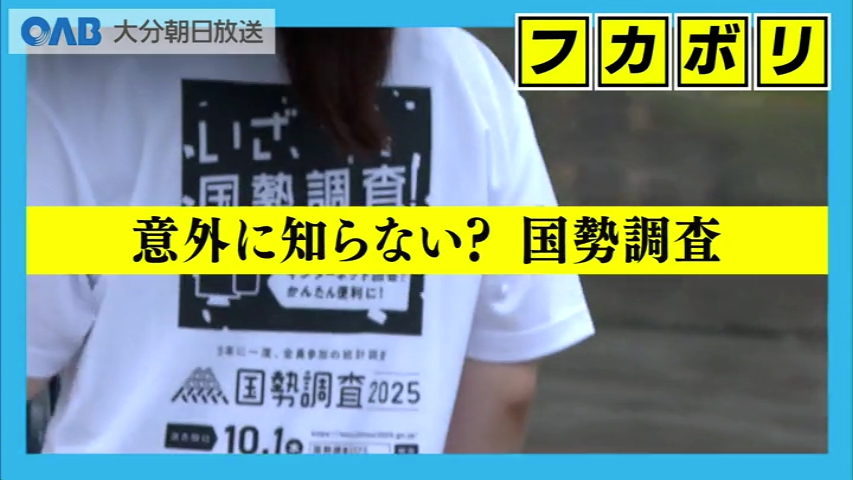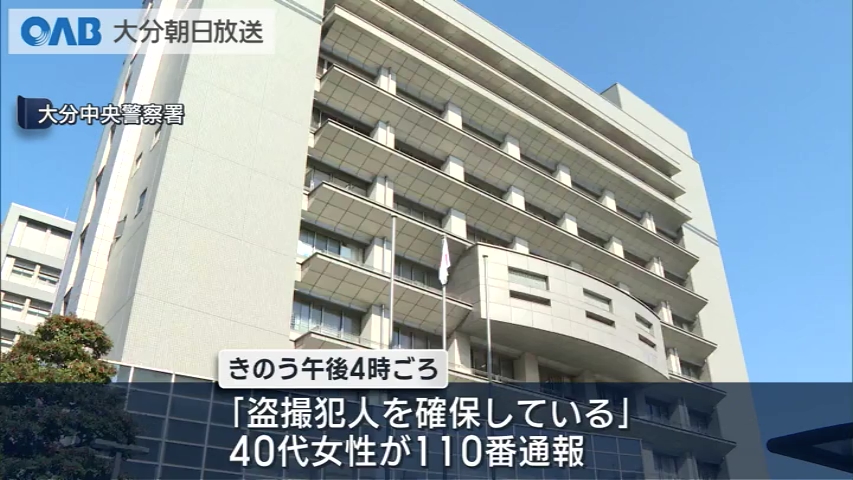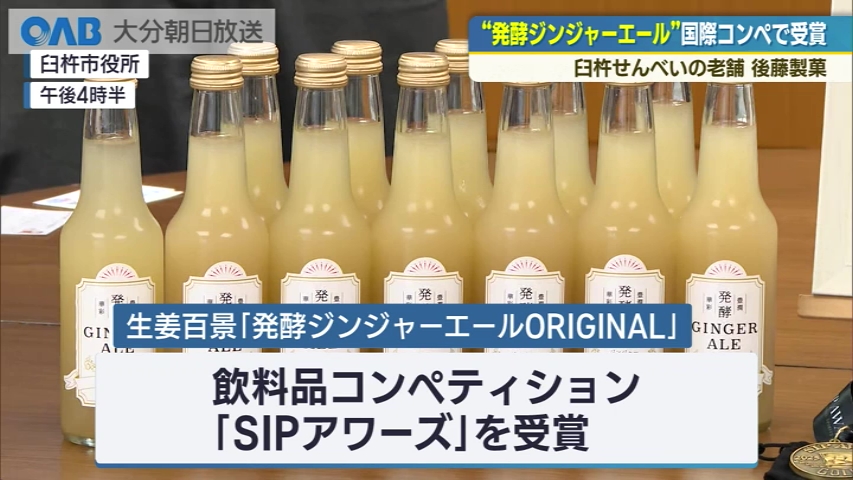NEWS
大分のニュース
9月23日(火) のニュース
2025年9月23日(火) 19:24
9月23日は「手話の日」 デフリンピック開催控え理解促進を 通訳者不足の課題も
2025年から9月23日が「手話の日」になったのはご存じでしょうか。
その手話を、「言語」として認識してもらおうというイベントが大分市でありました。
■佐藤アナウンサー:
「こちらでは、多くの人が手話を体験しています」
国連総会の「手話言語の国際デー」にあわせて、国は2025年から、9月23日を「手話の日」に制定。
JR大分駅前で県が主催した記念イベントが開かれました。
子どもが抱えているのは耳が聞こえない人のために作られたスピーカー。音を振動で感じることができます。
■20代:
「教育実習が大学生の時にあって、ろう学校で自分の名前を手話ですることがあった。披露したいな、お話したいなと思って」
■20代:
「マスクがついていると口の動きが分からないので、どうやって手話だけで伝えるか。表情も伝える最大の武器になると思ったので、聴こえない方々と話してみて難しいと実感しました」
参加した子どもが、教わった手話を披露してくれました。
■小学5年生:
「ありがとう」
■中学3年生:
「私の名前はらいとです」
現在、県内の手話通訳者は134人。それに対し、障害者手帳を持っている聴覚障害者は約5000人。すべての人が手話を必要としているわけではないそうですが、県の聴覚障害者協会には、年間約3000件の通訳依頼が入るそうです。
■県障害福祉課 伊東大樹さん:
「英語だったら簡単なハローとかサンキューとか言えると思うけど、そんな感じで手話も親しんで、簡単な手話を使っていただければ、障害がある方も暮らしやすい大分になっていくのではないか」
「手話は言語」「もっと身近に」いまこうした理解を深めようという活動が広がっています。
みなさん、この手話、何という意味か分かりますか?
ここからはフカボリです。
国は、9月23日を手話の日と定めました。
みなさんにも覚えてほしい簡単な手話も紹介しますが、その前に手話の日制定の背景を見ていきます。
今回手話の日と決まったのは「手話」イコール「言語」という理解を広めたいからなんです。
英語など外国語を学ぶように手話も言語のひとつとして学んでほしいという思いがあります。
さらに2025年11月には日本で初めて東京デフリンピックが開かれます。
この大会は聴覚障害者のアスリートが出場する国際的なスポーツ大会です。
こうした背景はありますが、今一番の課題は手話通訳者の数が足りていないことです。
県内の手話通訳者の年齢は現在、50~60代が中心で将来のためにも若い人の成り手が必要です。
また、仕事レベルで使えるようになるには5年ほどかかるケースもあります。
現在、各自治体が手話教室を開いているほか、県の協会は企業の依頼に対して出張の手話教室などをしているということです。
みなさんもぜひ簡単なあいさつから覚えてみてください。
その手話を、「言語」として認識してもらおうというイベントが大分市でありました。
■佐藤アナウンサー:
「こちらでは、多くの人が手話を体験しています」
国連総会の「手話言語の国際デー」にあわせて、国は2025年から、9月23日を「手話の日」に制定。
JR大分駅前で県が主催した記念イベントが開かれました。
子どもが抱えているのは耳が聞こえない人のために作られたスピーカー。音を振動で感じることができます。
■20代:
「教育実習が大学生の時にあって、ろう学校で自分の名前を手話ですることがあった。披露したいな、お話したいなと思って」
■20代:
「マスクがついていると口の動きが分からないので、どうやって手話だけで伝えるか。表情も伝える最大の武器になると思ったので、聴こえない方々と話してみて難しいと実感しました」
参加した子どもが、教わった手話を披露してくれました。
■小学5年生:
「ありがとう」
■中学3年生:
「私の名前はらいとです」
現在、県内の手話通訳者は134人。それに対し、障害者手帳を持っている聴覚障害者は約5000人。すべての人が手話を必要としているわけではないそうですが、県の聴覚障害者協会には、年間約3000件の通訳依頼が入るそうです。
■県障害福祉課 伊東大樹さん:
「英語だったら簡単なハローとかサンキューとか言えると思うけど、そんな感じで手話も親しんで、簡単な手話を使っていただければ、障害がある方も暮らしやすい大分になっていくのではないか」
「手話は言語」「もっと身近に」いまこうした理解を深めようという活動が広がっています。
みなさん、この手話、何という意味か分かりますか?
ここからはフカボリです。
国は、9月23日を手話の日と定めました。
みなさんにも覚えてほしい簡単な手話も紹介しますが、その前に手話の日制定の背景を見ていきます。
今回手話の日と決まったのは「手話」イコール「言語」という理解を広めたいからなんです。
英語など外国語を学ぶように手話も言語のひとつとして学んでほしいという思いがあります。
さらに2025年11月には日本で初めて東京デフリンピックが開かれます。
この大会は聴覚障害者のアスリートが出場する国際的なスポーツ大会です。
こうした背景はありますが、今一番の課題は手話通訳者の数が足りていないことです。
県内の手話通訳者の年齢は現在、50~60代が中心で将来のためにも若い人の成り手が必要です。
また、仕事レベルで使えるようになるには5年ほどかかるケースもあります。
現在、各自治体が手話教室を開いているほか、県の協会は企業の依頼に対して出張の手話教室などをしているということです。
みなさんもぜひ簡単なあいさつから覚えてみてください。