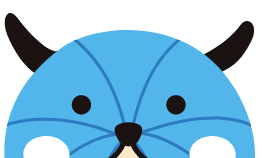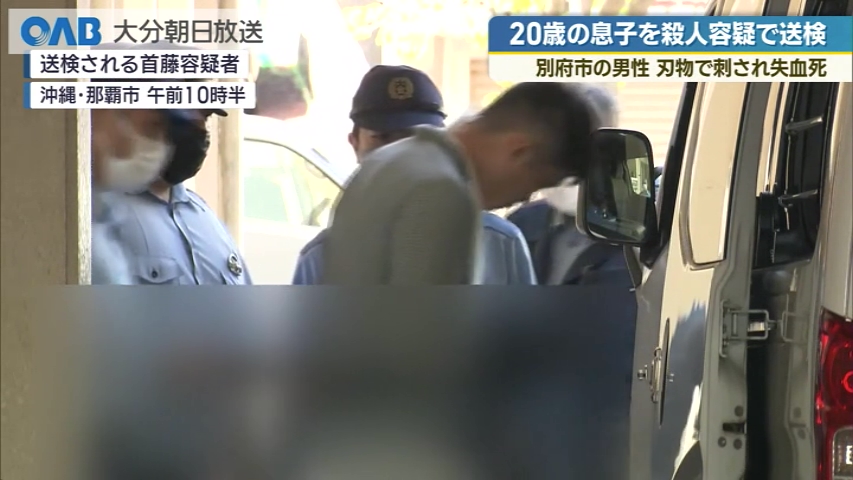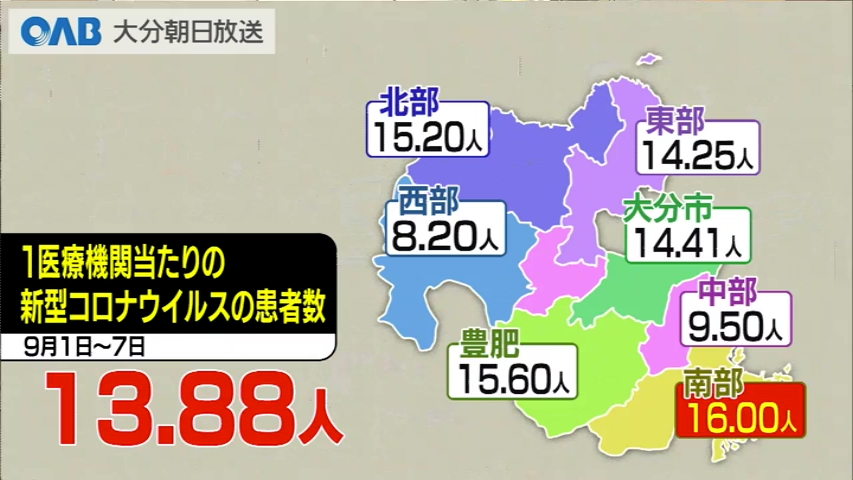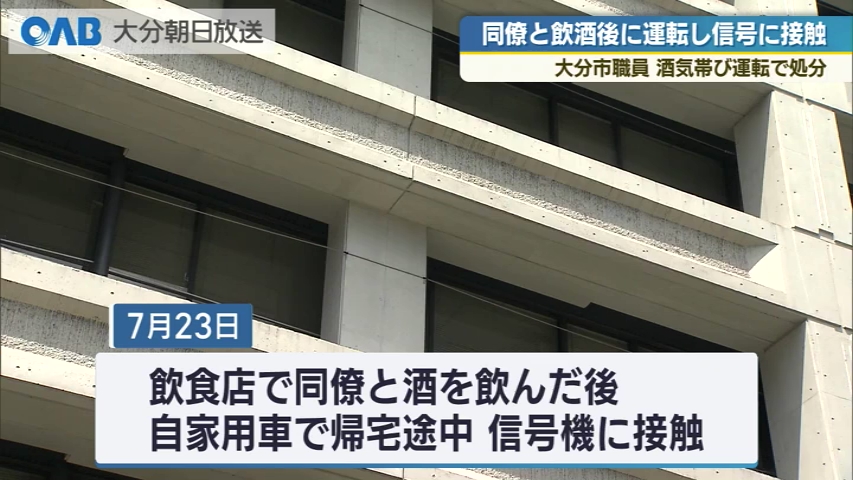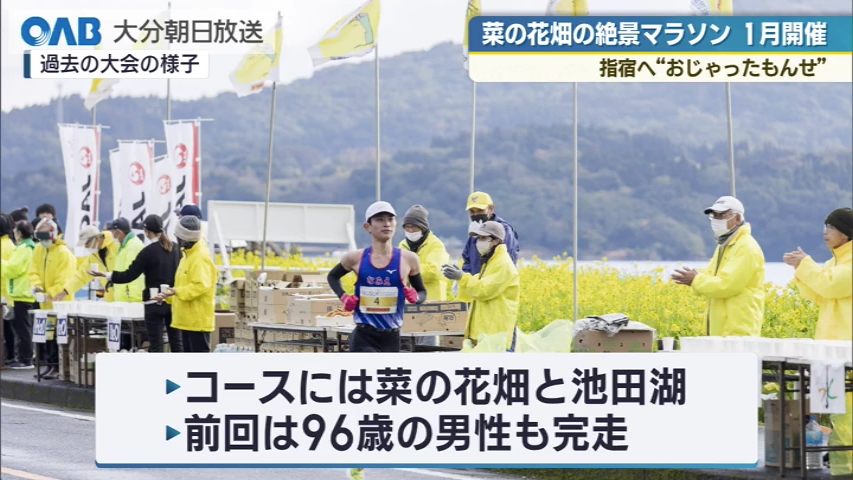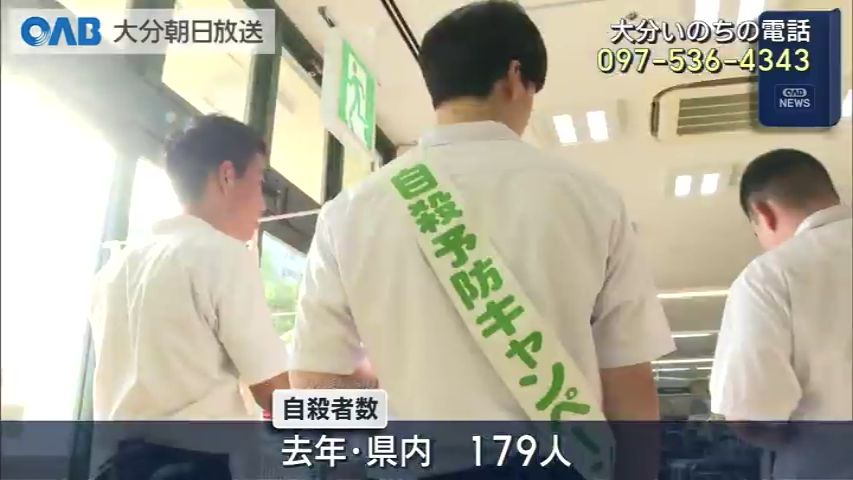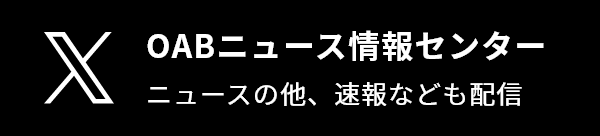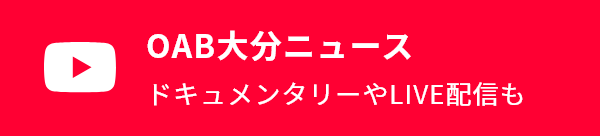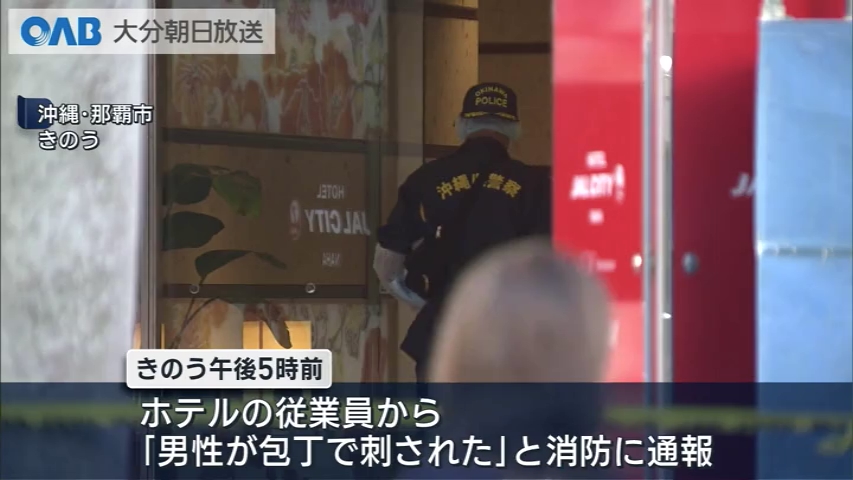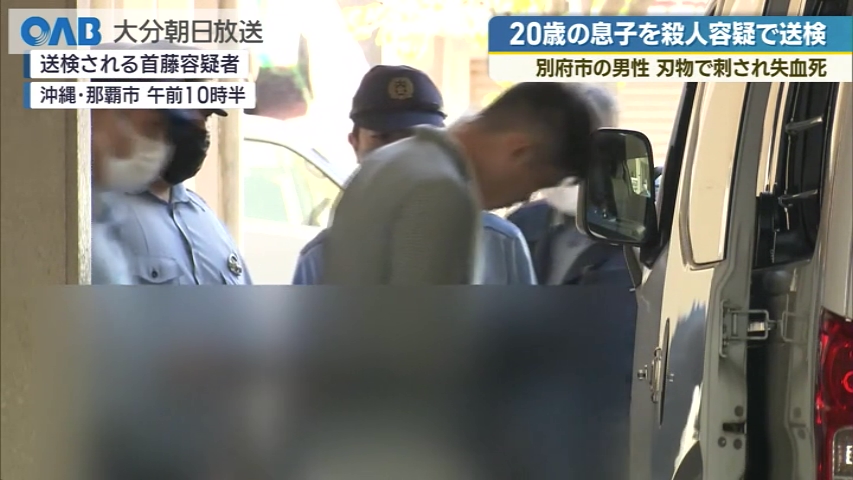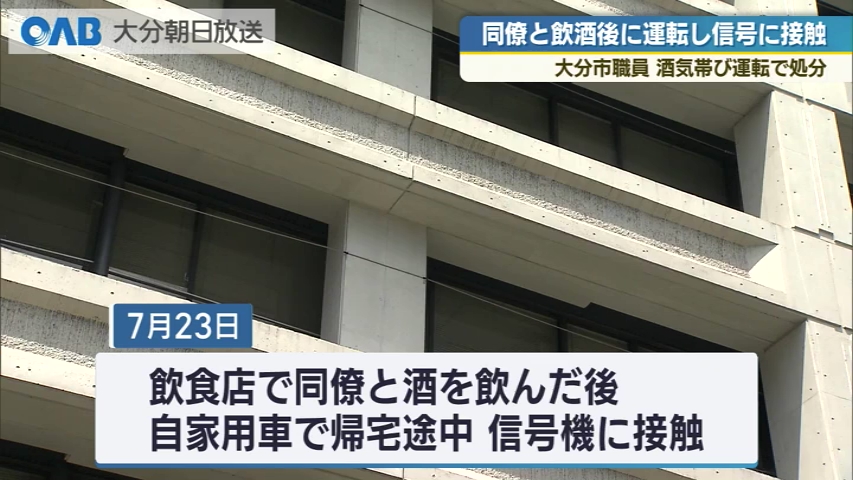NEWS
大分のニュース
9月10日(水) のニュース
2025年9月10日(水) 18:51
“人生最後の社会貢献”注目される遺贈寄付、“おひとりさま高齢者”の増加を背景に広
大分市で、遺贈寄付について学ぶセミナーが開かれました。いま注目されている遺贈寄付とは。
■下野アナウンサー:
「きょうから始まった遺贈寄付ウィーク。遺贈寄付について知ってもらうため、大分市でもセミナーが開かれています」
遺贈寄付とは、自分が亡くなったあと、信頼できる団体や地域に財産を託し、活用してもらう仕組みで、新しい社会貢献の形として注目されています。
セミナーは「遺贈寄付ウィーク」にあわせて大分市の葬儀会社が主催したもので、市民18人が参加しました。
行政書士など専門家が、寄付の具体的な活用方法や、寄付を実現させるために必要な遺言書の書き方を説明しました。
■大分市(89歳):
「社会の恵まれない人、例えば海外では戦争の遺児などに配りたいと思っている」
■大分市(78歳):
「一人暮らしの方が多いので、遺贈寄付があるというきょうの話を(世間話の中で)したいと思う」
■ファイン 茶屋元崇行統括本部長:
「新しい情報、新たな社会貢献として学ぶきっかけになれば」
寄付の受け皿のひとつである県社会福祉協議会は、こども食堂の運営や生活に困窮する世帯の支援などに役立てるとしています。
■県社協 衛藤真紀子さん:
「力を集結させる一つの手法としての遺贈。考えてみようかなという場合には、一度相談してもらいたい」
人生最後の社会貢献として広がる遺贈寄付。その背景と意義をフカボリします。
広がりを見せる遺贈寄付。背景には、ひとり暮らしの高齢者が増えている現状があります。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、大分県では25年後の2050年に、65歳以上の独居率が26%に達するとみられています。
葬儀業を運営するファインの茶屋元さんは、「家族の形が変化し、相続人がいない“おひとりさま”が増えている。遺産を託す先がない実情がある」と話します。
相続人のいない遺産は国庫に入ります。全国レガシーギフト協会によると、2015年は全国で336億円でしたが、これが10年後には、1015億円と3倍近くに膨らみました。
10日のセミナーに参加していた70代の方は「どうせなら大分のために使ってほしい。
遺贈寄付は自分が贈りたいと思うところに贈れるというのが良い」と話していました。
では、遺贈寄付で大分に貢献したいと考えた時どんな団体があるのでしょうか。
一例ですが、災害支援や子ども・若者支援、介護などの地域福祉が活用例として挙げられます。
県社協や、医療的ケア児の親の会「ここから」、子どもや若者を支援する「9sapo」などに寄付するとこういった支援につながります。
ただし、遺贈寄付には法的な手続きが必要です。
確実な方法は「遺言公正証書」の作成で、法律の専門家に相談することが勧められています。
茶屋元さんは「どういう人が助けを必要としているか、地域に目を向けてみてほしい。
自分が何が出きるのか調べることから始めると良いのでは」と話しています。
遺贈寄付は、遺産の一部や少額からでも可能です。将来に向けた選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。
■下野アナウンサー:
「きょうから始まった遺贈寄付ウィーク。遺贈寄付について知ってもらうため、大分市でもセミナーが開かれています」
遺贈寄付とは、自分が亡くなったあと、信頼できる団体や地域に財産を託し、活用してもらう仕組みで、新しい社会貢献の形として注目されています。
セミナーは「遺贈寄付ウィーク」にあわせて大分市の葬儀会社が主催したもので、市民18人が参加しました。
行政書士など専門家が、寄付の具体的な活用方法や、寄付を実現させるために必要な遺言書の書き方を説明しました。
■大分市(89歳):
「社会の恵まれない人、例えば海外では戦争の遺児などに配りたいと思っている」
■大分市(78歳):
「一人暮らしの方が多いので、遺贈寄付があるというきょうの話を(世間話の中で)したいと思う」
■ファイン 茶屋元崇行統括本部長:
「新しい情報、新たな社会貢献として学ぶきっかけになれば」
寄付の受け皿のひとつである県社会福祉協議会は、こども食堂の運営や生活に困窮する世帯の支援などに役立てるとしています。
■県社協 衛藤真紀子さん:
「力を集結させる一つの手法としての遺贈。考えてみようかなという場合には、一度相談してもらいたい」
人生最後の社会貢献として広がる遺贈寄付。その背景と意義をフカボリします。
広がりを見せる遺贈寄付。背景には、ひとり暮らしの高齢者が増えている現状があります。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、大分県では25年後の2050年に、65歳以上の独居率が26%に達するとみられています。
葬儀業を運営するファインの茶屋元さんは、「家族の形が変化し、相続人がいない“おひとりさま”が増えている。遺産を託す先がない実情がある」と話します。
相続人のいない遺産は国庫に入ります。全国レガシーギフト協会によると、2015年は全国で336億円でしたが、これが10年後には、1015億円と3倍近くに膨らみました。
10日のセミナーに参加していた70代の方は「どうせなら大分のために使ってほしい。
遺贈寄付は自分が贈りたいと思うところに贈れるというのが良い」と話していました。
では、遺贈寄付で大分に貢献したいと考えた時どんな団体があるのでしょうか。
一例ですが、災害支援や子ども・若者支援、介護などの地域福祉が活用例として挙げられます。
県社協や、医療的ケア児の親の会「ここから」、子どもや若者を支援する「9sapo」などに寄付するとこういった支援につながります。
ただし、遺贈寄付には法的な手続きが必要です。
確実な方法は「遺言公正証書」の作成で、法律の専門家に相談することが勧められています。
茶屋元さんは「どういう人が助けを必要としているか、地域に目を向けてみてほしい。
自分が何が出きるのか調べることから始めると良いのでは」と話しています。
遺贈寄付は、遺産の一部や少額からでも可能です。将来に向けた選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。