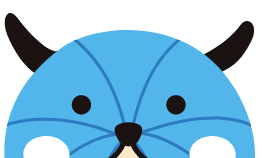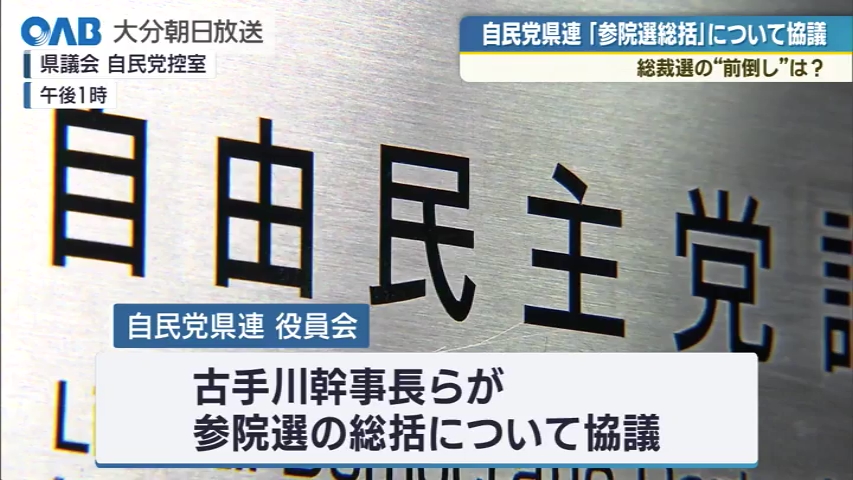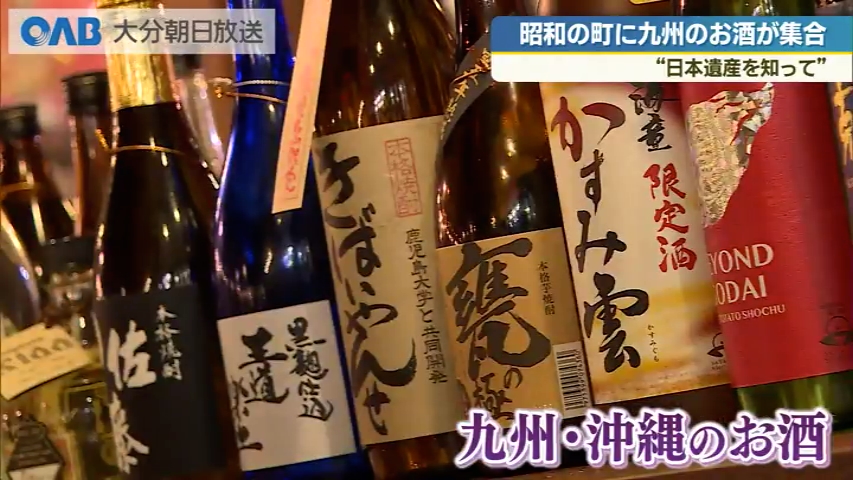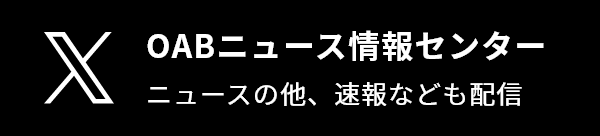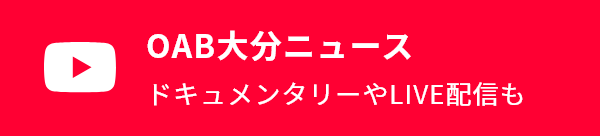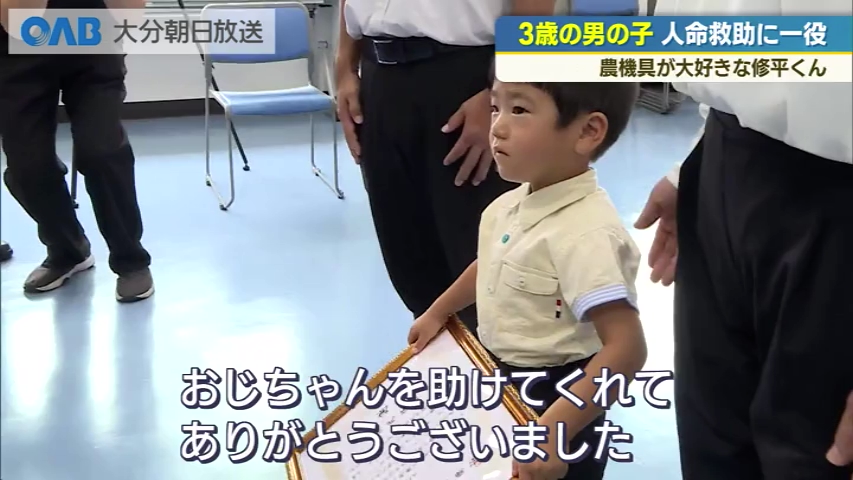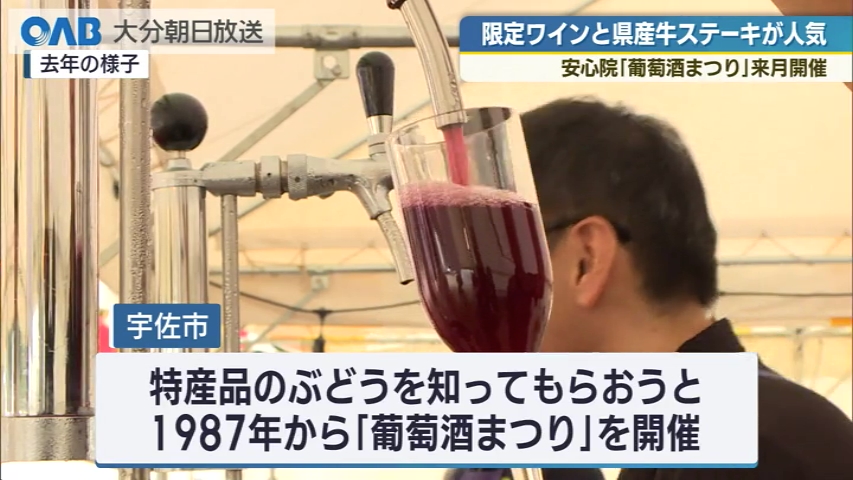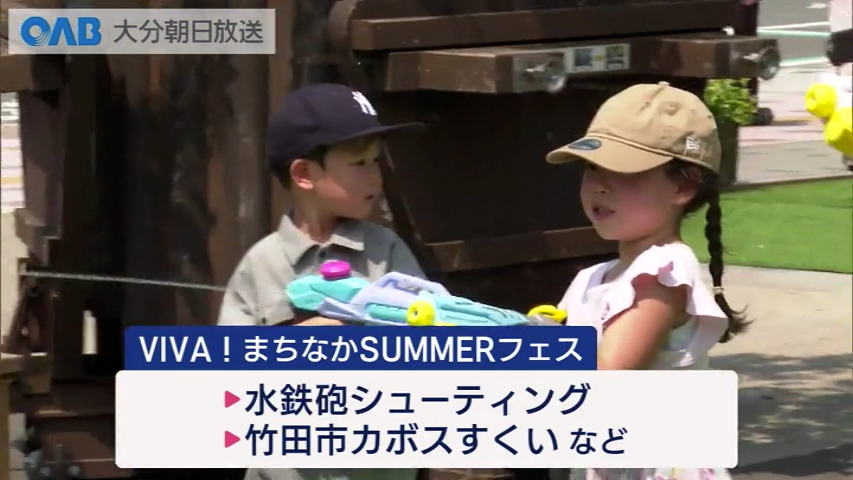NEWS
大分のニュース
9月1日(月) のニュース
2025年9月1日(月) 19:43
【フカボリ】防災の日 命を守るための心掛けとは
大分市では400以上の団体が防災訓練に臨みました。
毎月4千人以上が利用している府内こどもルーム。
訪れた親子も訓練に参加しました。
江藤アナ
「まさに今、南海トラフ地震が来て揺れている想定で訓練が始まりました。お父さん、お母さんが自身の体で子どもを守っています」
参加者
「子どもが一番心配。まだ小さいのでどう対応すればいいか分からない。(訓練があると)ありがたい」
「月齢によって必要なものが変わる。その時々で備品を確認しないと」
こちらのこどもルームでは、独自の対応マニュアルで万一の災害に備えているほか、倒れると危険なものを置かないようにしているそうです。
大分市では11年前から毎年9月1日の防災の日にあわせて訓練をしています。
学校や企業など参加する団体は徐々に増えていて、2025年は427カ所で行われました。
大分市防災危機管理課 工藤健一さん
「地震による多くの被害は家具などの転倒・落下。咄嗟の身の安全を守る行動を身に着けてほしい」
大きな災害から自分や大切な人の命を守るための日ごろの“心掛け”とは?専門家に聞きました。
ここからはフカボリです。
きょうの防災の日に合わせて各地で訓練がありました。
みなさんも学校などで揺れが来たら机の下にもぐる防災訓練をしたことがあると思います。
これは、突然の揺れから身を守る「シェイクアウト訓練」と言いまして、実は世界中で実践されています。
所要時間はわずか1分。
「身を低く」し「頭を守り」「動かない」この3つのポイントを覚えることで命を守るという、簡単で重要な訓練です。
大分市はここにさらにプラスワンすることを勧めています。
具体的には「プチ避難訓練」
◆避難口の確認
◆備蓄品が足りているか
◆危険な場所がないか、などです。
多くの人の意識が高まる時にこそ確認が重要なんですね。
こうした訓練は学校や企業など団体ですることが多いものですが専門家はこう指摘します。
大分大学理工学部の小林祐司教授は「ちょっと防災がキーワード。少しずつ話や準備を積み重ねてほしい」と呼び掛けています。
たとえば避難場所の確認です。
家族でこうしたことを共有しましょう。
特に子どもがいる家庭では「ここに行ったら動かないで」「ここに必ず迎えに行くからね」と話しておくと安心ですし避難経路を散歩するというのもいいですね。
また備蓄の確認では全員のあったらいいなと思うものを出し合って何をどれくらい用意するか調整することが望ましいそうです。
食料品や薬などは定期的な期限切れチェックもしておきましょう。
小林教授は「難しく考えるのではなく、日常会話や生活の中に取り込み、気軽に防災について話すのが大事」と話しています。
みなさんもぜひ普段の“少しずつ”を意識して取り組むようにしてください。
毎月4千人以上が利用している府内こどもルーム。
訪れた親子も訓練に参加しました。
江藤アナ
「まさに今、南海トラフ地震が来て揺れている想定で訓練が始まりました。お父さん、お母さんが自身の体で子どもを守っています」
参加者
「子どもが一番心配。まだ小さいのでどう対応すればいいか分からない。(訓練があると)ありがたい」
「月齢によって必要なものが変わる。その時々で備品を確認しないと」
こちらのこどもルームでは、独自の対応マニュアルで万一の災害に備えているほか、倒れると危険なものを置かないようにしているそうです。
大分市では11年前から毎年9月1日の防災の日にあわせて訓練をしています。
学校や企業など参加する団体は徐々に増えていて、2025年は427カ所で行われました。
大分市防災危機管理課 工藤健一さん
「地震による多くの被害は家具などの転倒・落下。咄嗟の身の安全を守る行動を身に着けてほしい」
大きな災害から自分や大切な人の命を守るための日ごろの“心掛け”とは?専門家に聞きました。
ここからはフカボリです。
きょうの防災の日に合わせて各地で訓練がありました。
みなさんも学校などで揺れが来たら机の下にもぐる防災訓練をしたことがあると思います。
これは、突然の揺れから身を守る「シェイクアウト訓練」と言いまして、実は世界中で実践されています。
所要時間はわずか1分。
「身を低く」し「頭を守り」「動かない」この3つのポイントを覚えることで命を守るという、簡単で重要な訓練です。
大分市はここにさらにプラスワンすることを勧めています。
具体的には「プチ避難訓練」
◆避難口の確認
◆備蓄品が足りているか
◆危険な場所がないか、などです。
多くの人の意識が高まる時にこそ確認が重要なんですね。
こうした訓練は学校や企業など団体ですることが多いものですが専門家はこう指摘します。
大分大学理工学部の小林祐司教授は「ちょっと防災がキーワード。少しずつ話や準備を積み重ねてほしい」と呼び掛けています。
たとえば避難場所の確認です。
家族でこうしたことを共有しましょう。
特に子どもがいる家庭では「ここに行ったら動かないで」「ここに必ず迎えに行くからね」と話しておくと安心ですし避難経路を散歩するというのもいいですね。
また備蓄の確認では全員のあったらいいなと思うものを出し合って何をどれくらい用意するか調整することが望ましいそうです。
食料品や薬などは定期的な期限切れチェックもしておきましょう。
小林教授は「難しく考えるのではなく、日常会話や生活の中に取り込み、気軽に防災について話すのが大事」と話しています。
みなさんもぜひ普段の“少しずつ”を意識して取り組むようにしてください。