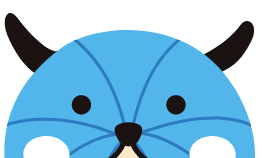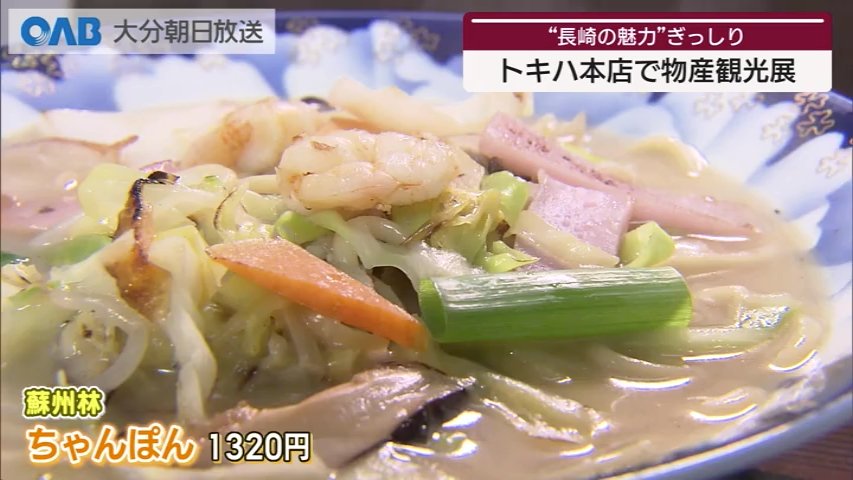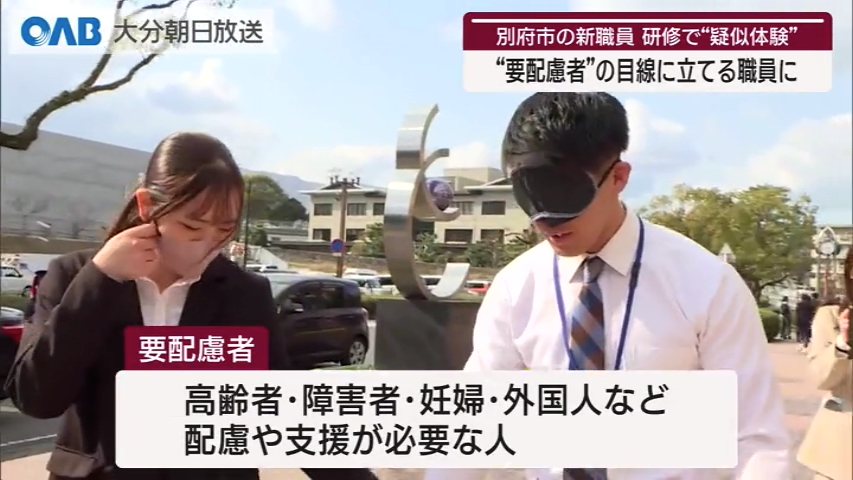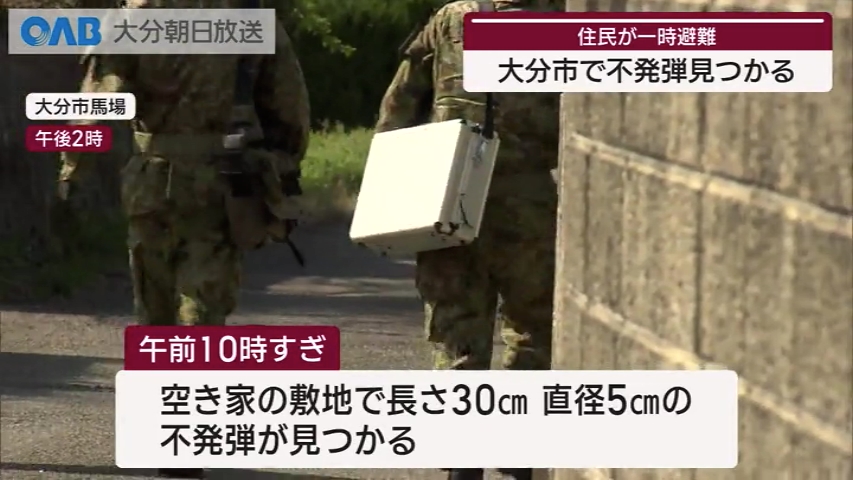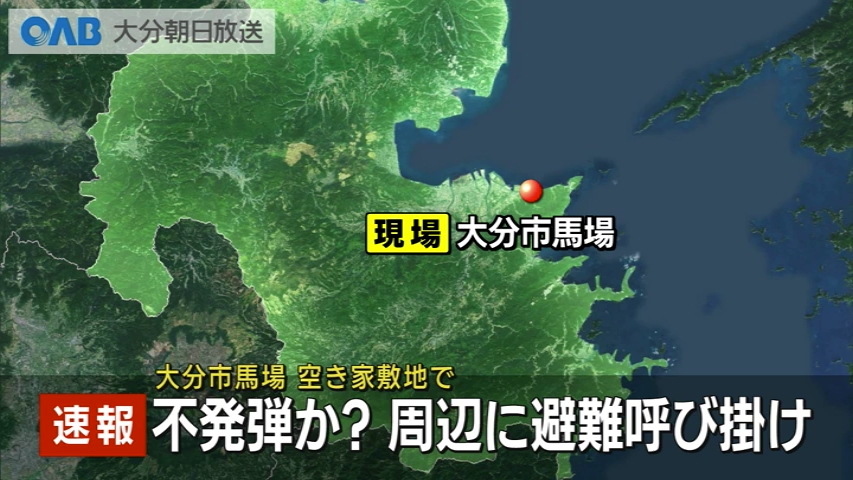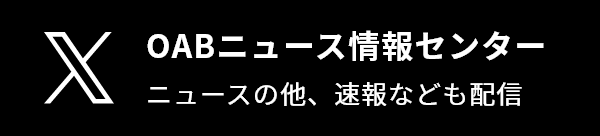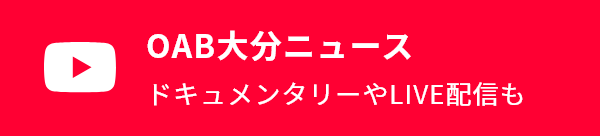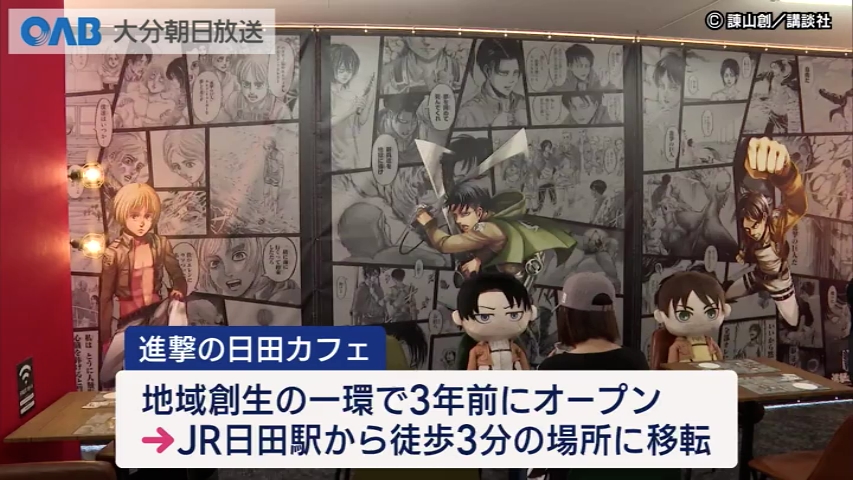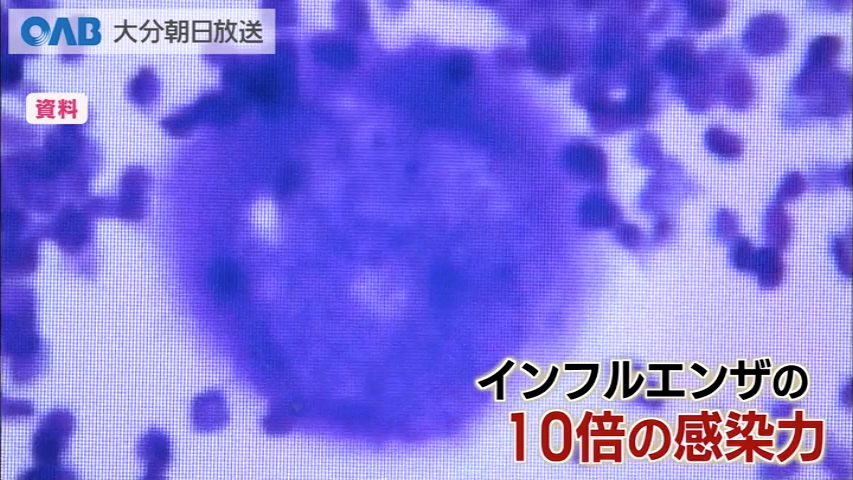NEWS
大分のニュース
4月3日(木) のニュース
2025年4月3日(木) 20:02
【大分】進む“新規就農”担い手を育成 そして人気の作物は?
高齢化などで減少傾向にある農業の担い手を育成しようと、大分市で「おおいた農業塾」が開講しました。
開講式には、30代から70代の44人が参加しました。栽培に関する知識や技術を習得し、農業従事者を育成することを目的に、今回で9回目。これまでに300人以上が卒業しています。
受講生は1年間にわたり、月に3回から4回、野菜や切り花の栽培や販売戦略などを学びます。
農業を営む人の減少が課題となる中、新規就農の今とこれからを解説します。自治体が進める「新規就農」への取り組み。その背景には農業に従事する人の減少があります。
県内では、農業就業人口は1995年には7万2千人あまりでしたが、2020年には2万1千人ほど。25年間で7割減っています。高齢化や担い手不足が課題です。
一方で、新規就農者、新たに農業を始めた人の数は2023年に285人。この数は年々増加傾向です。この年は女性の新規就農者数が過去最多でした。年代では、7割が50代以上という傾向があります。
実際に農業を始めた方に話を聞きました。40代の男性です。サービス業の会社を2年前に退職し、津久見市内でミカンのサンクイーンの栽培を始めた方です。
この男性は「きっかけは市が開催した就農フェア。農業は頑張った分だけ結果が出るし、家族との時間も増えた。今後他の品種にも挑戦していきたい」と話します。
新規就農で、ダントツに多いのがピーマンです。他の野菜と比べると、設備の初期費用が少なくて済み、年間を通して栽培や流通が行われているからだそうです。
他には県産ブランドイチゴのベリーツや、梨、味一ねぎなども多いそうです。
そして、就農の動きは個人だけではありません。企業も進出しています。食品や土木業界など、年間20社程度が県内で農業分野に参入しています。
例えば、3月には、ファーマインドという会社が参入を表明。東京に本社がある物流会社で、国東市内で梨の栽培を手掛けます。ナシ園として国内最大級・18ヘクタールの規模で、5年後の初収穫を目指しています。
開講式には、30代から70代の44人が参加しました。栽培に関する知識や技術を習得し、農業従事者を育成することを目的に、今回で9回目。これまでに300人以上が卒業しています。
受講生は1年間にわたり、月に3回から4回、野菜や切り花の栽培や販売戦略などを学びます。
農業を営む人の減少が課題となる中、新規就農の今とこれからを解説します。自治体が進める「新規就農」への取り組み。その背景には農業に従事する人の減少があります。
県内では、農業就業人口は1995年には7万2千人あまりでしたが、2020年には2万1千人ほど。25年間で7割減っています。高齢化や担い手不足が課題です。
一方で、新規就農者、新たに農業を始めた人の数は2023年に285人。この数は年々増加傾向です。この年は女性の新規就農者数が過去最多でした。年代では、7割が50代以上という傾向があります。
実際に農業を始めた方に話を聞きました。40代の男性です。サービス業の会社を2年前に退職し、津久見市内でミカンのサンクイーンの栽培を始めた方です。
この男性は「きっかけは市が開催した就農フェア。農業は頑張った分だけ結果が出るし、家族との時間も増えた。今後他の品種にも挑戦していきたい」と話します。
新規就農で、ダントツに多いのがピーマンです。他の野菜と比べると、設備の初期費用が少なくて済み、年間を通して栽培や流通が行われているからだそうです。
他には県産ブランドイチゴのベリーツや、梨、味一ねぎなども多いそうです。
そして、就農の動きは個人だけではありません。企業も進出しています。食品や土木業界など、年間20社程度が県内で農業分野に参入しています。
例えば、3月には、ファーマインドという会社が参入を表明。東京に本社がある物流会社で、国東市内で梨の栽培を手掛けます。ナシ園として国内最大級・18ヘクタールの規模で、5年後の初収穫を目指しています。