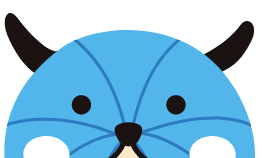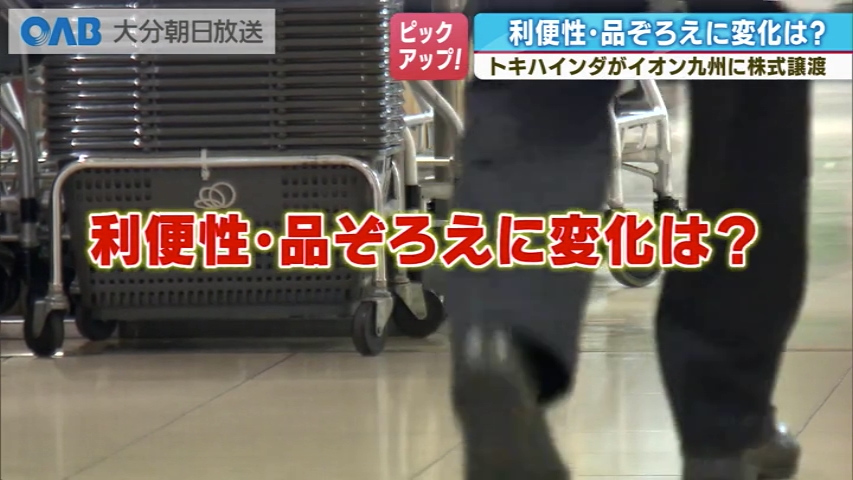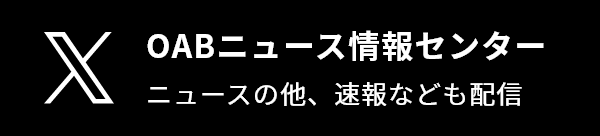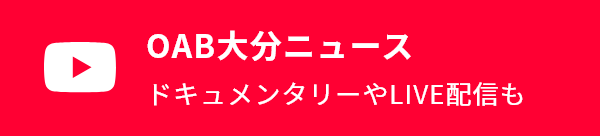NEWS
大分のニュース
10月24日(金) のニュース
2025年10月24日(金) 19:52
孤島に立つ灯台「水ノ子島灯台」 国の重要文化財に答申 明治の建設“屈指の難工事”
佐伯市の沖合にある水ノ子島灯台が、国の重要文化財に指定されことになりました。
豊後水道のほぼ中央、九州と四国の間に浮かぶ水ノ子島に立つこの灯台。
高さはおよそ40メートルで、明治時代に造られた石造りの灯台です。
「日本の灯台50選」にも選ばれています。
24日、国の文化審議会は、水ノ子島灯台を重要文化財に指定するよう文部科学大臣に答申しました。
官報への告示を経て正式に指定されますが、県内の灯台としては初めてです。
水ノ子島灯台が初めて点灯したのは、今から121年前の明治37年。
光の到達距離は37キロに及び、当時は東洋一の性能を誇りました。
2002年に耐震工事が行われ、翌年には太陽光発電に切り替えられました。
現在も太陽の力で豊後水道を照らしています。
航行する船の安全を守り続ける水ノ子島灯台。その歴史的価値を詳しく解説します。
国の重要文化財は県内に90あります。
国の重要文化財には、歴史上・芸術上・学術上価値の高い建造物などが指定されます。
例えば大分市の柞原八幡宮。写真の本殿をはじめ12棟の建物が指定されています。
また、日田市豆田町の草野家住宅は、大型の商家建築として高く評価されています。
3年前に指定された中津市の耶馬渓橋や、1267年、鎌倉時代に建てられた九重塔など、県内各地に歴史を伝える建造物が数多くあります。
そして今回、新たに国の重要文化財に指定されるのが、佐伯市の水ノ子島灯台です。
豊後水道に浮かぶ孤島・水ノ子島に立つこの灯台は、1904年、明治37年に建造されました。
灯台としては珍しい石造りで、120年前の姿のまま、今も現役で海を照らし続けています。
白と黒の縞模様も当時から変わらず、歴史的価値が改めて評価されました。
この灯台は、灯台建設史上でも屈指の難工事だったといわれています。
使用された石は、山口県徳山の黒髪島で採れた御影石。
佐伯市下梶寄の浜まで運んで加工し、さらに孤島の水ノ子島まで船で運び上げたということです。
着工から完成までに4年を要しました。
水ノ子島灯台は、官報での告示を経て正式に重要文化財に指定される予定です。
豊後水道のほぼ中央、九州と四国の間に浮かぶ水ノ子島に立つこの灯台。
高さはおよそ40メートルで、明治時代に造られた石造りの灯台です。
「日本の灯台50選」にも選ばれています。
24日、国の文化審議会は、水ノ子島灯台を重要文化財に指定するよう文部科学大臣に答申しました。
官報への告示を経て正式に指定されますが、県内の灯台としては初めてです。
水ノ子島灯台が初めて点灯したのは、今から121年前の明治37年。
光の到達距離は37キロに及び、当時は東洋一の性能を誇りました。
2002年に耐震工事が行われ、翌年には太陽光発電に切り替えられました。
現在も太陽の力で豊後水道を照らしています。
航行する船の安全を守り続ける水ノ子島灯台。その歴史的価値を詳しく解説します。
国の重要文化財は県内に90あります。
国の重要文化財には、歴史上・芸術上・学術上価値の高い建造物などが指定されます。
例えば大分市の柞原八幡宮。写真の本殿をはじめ12棟の建物が指定されています。
また、日田市豆田町の草野家住宅は、大型の商家建築として高く評価されています。
3年前に指定された中津市の耶馬渓橋や、1267年、鎌倉時代に建てられた九重塔など、県内各地に歴史を伝える建造物が数多くあります。
そして今回、新たに国の重要文化財に指定されるのが、佐伯市の水ノ子島灯台です。
豊後水道に浮かぶ孤島・水ノ子島に立つこの灯台は、1904年、明治37年に建造されました。
灯台としては珍しい石造りで、120年前の姿のまま、今も現役で海を照らし続けています。
白と黒の縞模様も当時から変わらず、歴史的価値が改めて評価されました。
この灯台は、灯台建設史上でも屈指の難工事だったといわれています。
使用された石は、山口県徳山の黒髪島で採れた御影石。
佐伯市下梶寄の浜まで運んで加工し、さらに孤島の水ノ子島まで船で運び上げたということです。
着工から完成までに4年を要しました。
水ノ子島灯台は、官報での告示を経て正式に重要文化財に指定される予定です。