講師紹介
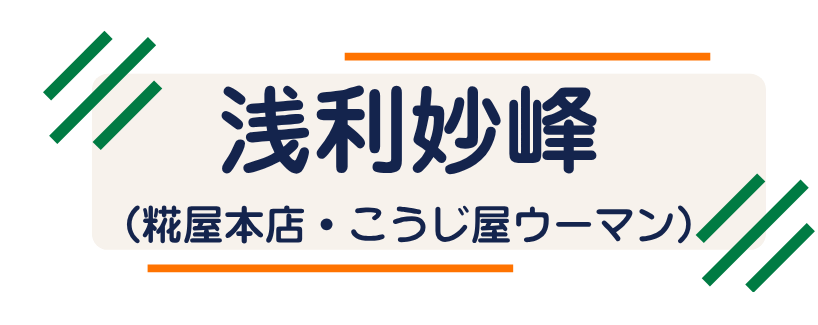

元禄2年創業・糀屋本店の女将として、糀の魅力を現代に伝える発酵文化の第一人者。
塩糀や甘糀を使った手軽で美味しいレシピの提案や酵素の働きを活かした健康づくりの知識を、国内外で発信。食と科学、伝統と未来をつなぐ学びの場を広げている。メディア主演や著書、受賞歴も多数。
大分の“おいしい”を支える発酵
和食が並ぶ食卓には、味噌や醤油など、発酵食品を使った料理が欠かせません。
「発酵食品」は、麹菌や酵母など、微生物の働きによってつくられる食品で、食材本来のおいしさやうまみが増すだけでなく、我々の健康にもよい影響を与えてくれるといわれています。
大分には、「だんご汁」や「りゅうきゅう」のように、味噌や醤油などの発酵食品を使った郷土料理が多くあります。また、「あゆうるか」や「酒まんじゅう」などは発酵技術を生かしてつくられてきた郷土料理です。
先人たちの知恵と工夫が詰まった「発酵食品」は、地域の暮らしに溶け込み、地域の食文化を支えてきました。
.png)
大分の発酵の歴史
日本の発酵文化は、酒づくりから始まったとされています。713年に編纂された「播磨国風土記」には、神様にお供えした米にカビが生え、それで酒をつくったことが記されています。大分でも、中世にはすでに「豊後練貫酒」や「麻地酒」などの酒づくりが行われていました。また、杵築市の「どぶろく祭り」や由布市の「甘酒祭り」のように、地域に根ざした祭りの中には、酒づくりが行われるものもあります。
味噌や醤油も昔から家庭でつくられていたと考えられますが、特に産業としての展開は、1600年に臼杵藩の家臣・可兒孫右衛門とその子息・可兒傳蔵による「鑰屋」(現・カニ醤油)創業により始まったと伝えられています。また、豊後佐伯藩・船頭衆の頭として藩主・毛利公に仕えていた吉左衛門信義は、1689年に大分県佐伯市にて「こうじ」専門店の糀屋本店を創業しました。
このように、大分でも古くから発酵文化が生活の中に根づいてきました。
.png)
可能性は無限大!? 発酵のヒミツQ&A
.png)
.png)
.png)
簡単♪ 発酵食品を使ったアレンジレシピ
11月19日は おおいた食(ごはん)の日
大分県食育推進条例では11月19日を「おおいた食(ごはん)の日」、おおいた食の日を含む1週間を「おおいた食育ウィーク」と定めています。
「おおいた食の日」や「おおいた食育ウィーク」を中心に、県内で食育の普及啓発を行っています。
- 主 催
- 大分県(生活環境部食品・生活衛生課)
- お問い合わせ
- 大分朝日放送株式会社
- TEL:097-538-6150(平日 10:00~16:00)
- ※本事業は、大分県から委託を受けて大分朝日放送(株)が実施しています。
▼ 詳細設定(ナビ用) ▼
| 入力欄 | 説明 | |
|---|---|---|
| ナビの背景色 | #038989 | ナビの背景色をカラーコードや色名で指定してください |
| ナビの文字の色 | white | ナビの文字色をカラーコードや色名で指定してください |

.png)
.png)

